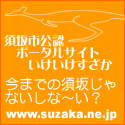ーであい ふれあい まなびあいー
カテゴリ: 須坂市民学園
2024/04/05
市民学園絵画クラブと水墨画家とのコラボ絵画展(5月10日~23日)
須坂市民学園生及び市民学園同窓会員からなる市民学園絵画クラブと水墨画家南澤廣江氏とのコラボ絵画展を開催します![]() ぜひお越しください
ぜひお越しください![]()
と き 2024年5月10日(金)~23日(木)
午前9時~午後5時
※最終日は正午まで
ところ 生涯学習センター2階ロビー
内 容 ・クラブ員の自由作品
・南澤廣江氏の山河等を中心とした水墨画
入場料 無料
問合せ ☎285-0605(尾川)

2024/03/13
生涯学び続けよう ~須坂市民学園卒業式~
3月、各学校では卒業式が行われ新たな気持ちを抱いた卒業生が旅立ちました![]()
そして生涯学習センターでも卒業を迎えた方々がいます。
3月9日(土)須坂市民学園卒業式が行われ、23名の卒業生が5年間の学びを終えました![]()


市民学園の柱である「であい ふれあい まなびあい」を学園生活の中で体験し、クラスの仲間と笑顔で卒業を迎えました![]()

一人一人名前を読み上げられ、小林学園長から卒業証書を受け取りました。


卒業生代表の飯塚さんは「入学した当初は何もわからず戸惑うことが多かったが、徐々に学園生活に慣れ様々な学びを体験することができた。」と思い出を振り返りました![]()
飯塚さんの挨拶に共感するように卒業生も時々うなずいていました![]()
そして記念品として5年間の思い出が詰まったDVDを受け取り学園生からの大きな拍手で見送られました![]()

市民学園では18歳以上の方たちが楽しく学習をしています。
年に2回、クラス内で館外学習会(社会化見学)の行先も考えたりと充実した学園生活を送ることができます!
皆さんも新しい仲間とともに学園生活を体験してみませんか![]()
現在、2024年度市民学園新入生を募集しています!
皆さんのお申込みお待ちしております!![]()

2024/01/22
須坂市民学園公開講座~参加者募集~
須坂市民学園公開上映会『シルク時空(とき)をこえて』
明治から大正、昭和にかけて日本のシルク産業が繁栄した信州を中心に、
飛騨、上州、横浜、福島、そして世界へと絹の歴史を巡る物語を上映します。
市民学園生のほかにどなたでも参加が可能です。
参加を希望される方は、申込期間内に生涯学習推進課へお申込ください![]()
・日時:2月17日(土)午後1時45分から午後3時30分(開場:午後1時30分)
・場所:生涯学習センター3階ホール
・定員:40人(申込順)
・申込期間:2月5日(月)~12月15日(木)
・申込・問合せ:生涯学習推進課 ☎026-245-1598
2023/12/07
須坂市民学園公開講演会~参加者募集~
毎年この時期にお招きしている堀井正子さんの講演です。
堀井さんが執筆されているエッセイ集などから、季節の変化や自然の美しさ、
愛情あふれる言葉や方言のもつあたたかさなどについてお話いただきます。
市民学園生のほかにどなたでも参加が可能です。
参加を希望される方は、申込期間内に生涯学習推進課へお申込ください![]()
・日時:12月16日(土)午後2時から午後3時30分
・場所:生涯学習センター3階ホール
・演題:「ことばの豊かさ・あたたかさ~365日の季節を追って~」
・講師:堀井正子さん(文学研究家)
・定員:30人(申込順)
・申込期間:12月5日(火)~12月14日(木)
・申込・問合せ:生涯学習推進課 ☎026-245-1598
2023/10/20
12月2日(土曜日)須坂市民学園祭!!
須坂市民学園では、学級活動やクラブ活動など日頃の活動の成果を発表する機会として市民学園祭を開催します![]()
お気軽にお越しください![]()
日時 ステージ発表12月2日(土曜日)午後1時~午後3時30分
展示発表12月14日(木曜日)~12月27日(水曜日)
場所 生涯学習センター
入場料 無料
申込 不要
問合せ 生涯学習推進課(電話026-245-1598)
:: 次のページ >>
検索
カテゴリ
リンクブログ
須坂のリンク
- いけいけすざかブログ一覧

- 須坂といえば・いけいけすざか 須坂市公認ポータルサイト
https://www.suzaka.ne.jp/

- 須坂市公式ホームページ https://www.city.suzaka.nagano.jp/

- 須坂新聞 https://www.suzaka.ne.jp/news/